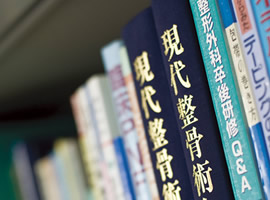アスレティックトレーナーコース
※※【NEW】アスレティックトレーナー資格取得後の活躍は「卒業生の活躍」をチェック!※※
有明での学び

アスレティックトレーナー(AT)は、スポーツ現場において競技者がケガをした際の応急処置やコンディショニング、リコンディショニングを行う、スポーツ現場と医療のパイプ役となる存在です。また、ケガが起こる前の予防のトレーニングや教育を行うのも仕事です。
鍼灸学科、柔道整復学科では、学科の科目において、人体の構造や機能について様々な教育を受けますが、これに加えて本コースにおいて、スポーツ現場で必要とされる知識や技術を修得することで、スポーツ選手やスポーツを行い一般の人々に対して適切な治療とケアを行うことのできる、信頼されるトレーナーを目指すことがでいます。
カリキュラム
※授業は毎週土曜日の他、夏休み等に集中します。
PICK UP 授業
テーピング
![]() 授業動画1(Instagramに移動します)
授業動画1(Instagramに移動します)
![]() 授業動画2(Instagramに移動します)
授業動画2(Instagramに移動します)
アスレティックトレーニング
実習
- サッカー 川崎フロンターレ ユースチームで見学実習を行っています。
- アメリカンフットボールクラブ ラングラーズのサポートを行っています。
アスレティックトレーナーの仕事
スポーツ現場におけるケガや事故を「予防」
個々の選手の筋力や柔軟性、ウォーミングアップ、クーリングダウンは十分であるか、体重は適切に保たれているか、正しい動作は獲得されているか、路面の性質にあったシューズが選択されているかなど、ケガや事故につながる要素をできる限り少なくなるように指導します。
ケガや事故が発生した時に適切な「救急処置」
どれだけ十分な予防をしていたとしても、ケガや事故を100%防ぐことはできません。またスポーツ現場では、命にかかわる緊急事態に遭遇することも少なくありません。正しく傷害の性質や程度を評価し、適切な救急処置を行うこともアスレティックトレーナーの重要な仕事です。
競技復帰への「アスレティックリハビリテーション」
ケガをした後、再びスポーツ現場に復帰するためには、日常生活への復帰を目標としたメディカルリハビリテーションだけでは十分とはいえません。そのスポーツで求められる身体機能・体力・技術を総合的に回復させるためのリコンディショニングが必要です。また現場へ復帰した後も、再発予防を目的としたテーピングや動作指導を行うなど、競技者が再びベストなコンディションで競技できるようサポートしていきます。
このように、アスレティックトレーナーには様々な知識と技術そして能力が求められ、スポーツ現場で働くスタッフの中でもスポーツ医科学の知識を持った人材として、活躍の場が広がっています。
取得を目標とする資格
アスレティックトレーナーは、財団法人日本スポーツ協会が認定する資格です。保健医療学部では所属学科の必要科目に加え、本コースの指定科目を修得することにより、同資格の受験資格を得ることができます。
- (公財)日本スポーツ協会 公認アスレティックトレーナー 受験資格
- (公財)日本スポーツ協会 公認スポーツプログラマー 受験資格
- (公財)健康・体力づくり事業財団 健康運動実践指導者 受験資格
- 日本赤十字社 赤十字救急法救急員